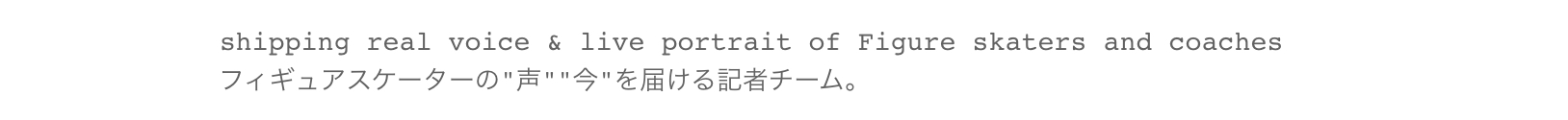Pigeon Post interviewed Tatsuki MACHIDA 町田樹選手 @ Kansai University in Senriyama 関西大学千里山キャンパス.
thanks to: JAPAN SPORTS for photos, PAJA for illustrations
by AIKO SHIMAZU 島津愛子
November 5, 2013 in Osaka

Tatsuki MACHIDA @ 2013 Skate America
町田樹選手の前回の取材で、「250点を超えた暁には またインタビューを」と粋なお約束を頂いたのが6月。シーズン始めの10月中旬、ISUグランプリシリーズ・スケートアメリカで、その暁が早々に、あるいは盛大にやって来ました!「265.38」で優勝された2週間後に、再び赴いた関西大学千里山キャンパスに待っていたのは、23歳の町田樹さんという、様々なる方面から注ぎ込む 知の大海。競技者・演者・創り手として その知を形と成している、真実の力。
前回も 幾重にも広がるお話にワクワクしましたが、それは大河の一滴で、今回のお話も氷山の一角でしょう⋯
どうぞ、皆さんも「次に何が出て来るのかな?」とワクワクしながら、樹さんとの1時間を御一緒下さい。
(16000字を3ページに分けました)
前回の取材は ☞ こちら (12000字)
PP: まずは、マストなところから、盤石の状態となった四回転について、お伺いします!「技を極めよう」としている、他の運動をがんばってるキッズにもためになると思うんですけれども、このオフの期間でどのように習得されていったのでしょう。
TM: 一番 四回転の安定に繋がったのは、「コンパルソリー」であることは間違いなくて。やはり、コンパルソリーをすることによって自分の身体にとても敏感になり、自分の身体に「センサー」を細かく配置することが出来たということですね。
PP: それも、陸上とは違う、氷に乗った上でのバランスですよね?
TM: そうです、スケート靴も自分の体と一体化している、という風に捉えた上での「身体」です。
TM: まず、コンパルソリーって、フィギュアスケートの「meditation(英語本来の意味は宗教的な"瞑想"の他、"熟考"・"深慮"の意も)」だと思っていて。
PP: フィギュアスケートの「こころ」。どんな練習でしょう。
TM: とても難しいんですけど、コンパルソリーをやりつつ、自分の身体の皮膚を全部はいで、「人体模型」——理科室にあるような、
PP: さらけ出した人いましたね、
TM: その、内蔵とか筋肉の繊維とか脳みそが見えた状態に、自分の身体をイメージするんです。この筋肉がこう動くことによってうまくターンが描ける、とか、こう動かしてしまうとバランスを崩してしまう、とか、自分の身体を人体模型レベルで考えて。
それが出来てくると、今度は筋肉とか内蔵といったもの全てを排除し、「骸骨模型」で自分の身体を考えるんですね。この関節がこう動くからうまくエッジに乗れる、この関節がこう動いてここの関節をこう動かしてしまうと身体のバランスが崩れて難しいよな、っていうのを理解するようになるんです。
それが出来てくると、その次は「自分の心身との対話」。無我夢中、無心で、ほんとに「無」の状態になってやることもあれば、自分の今の状況・コンディションを分析し、「これから試合に向けてどのように自分が歩んで行けばいいのか」と想い描きながらやったり。
そういうことがコンパルソリーを通して出来るようになったので。
TM: それがジャンプとかにも応用できるようになったんですね。ジャンプを失敗した時に、「今なんで失敗したのか」と。それは、この筋肉がこう動いていたりこの関節がこう動くことによって失敗を招いた、と。そうではなく、この筋肉この関節をこう使うことによって成功に導くことが出来る、と自己分析できるようになって。
自分の身体をより理解し、より敏感になった、ということが四回転や四回転以外の技にも繋がってますね。スピンも、まだまだですけど回転が速くなってますし、他のジャンプの安定度もかなり増しているので。それはほんとに、コンパルソリーを含め 今シーズンの一つのテーマでもある「凡事徹底」の功績だと思います。
PP: 徐々に全ての面に良い効果が。
TM: そうですね。今は、このようなフィギュアスケート界が形成されていますけど、時代を遡ると 原点はコンパルソリーなので。氷に図形を描く——まさに figure(図形) skating、という『原点回帰』、そこに立ち返った時に、全てに応用が利く。コンパルソリーは大事だな、と今シーズンは実感しましたね。
PP: ⋯陸の運動だと、否随意筋を随意筋にするには、体作りとフォームの確認の積み重ね、それしかないですけれど、「コンパルソリー」で全身精密機器化を図った、っていうのがスポーツファン的にはおもしろいです!
TM: そう、もちろん、コンパルソリーで筋肉付けたりは出来ないですけど、どうしたらそうなるのかという「自己分析」と、自分の身体に対しての「プログラミング」ですよね、
PP: ソレだ!
TM: (笑) ソレは、出来るのかな、とは思います。どの筋肉が足りないのか、とか、そこでアナライズされた情報を陸トレに転用したり。現在のフィギュアスケートの技は全てがコンパルソリーから派生し、そこから応用されていると思うので。
例えば、エッジ一つとっても、「トゥ(爪先)-中間-踵」と漠然と捉えるのではなくて、ほんとにピンポイントで「このエッジのココ」とか、自分の中で明確に区別されています。四回転を飛ぶ際には、ピンポイントでココのエッジに乗ることによって絶対に外さないな、とか、スピンは、このエッジのこの部分に安定して乗っていれば、もっと速く回れる、とか、分かってきたということですかね。
PP: ⋯いよいよマシンになってきた、という。
TM: 人間の体には「痛点」がありますよね、針治療がなんで痛くないかと言うと、人体に配置されている痛点の密度以上に針が細いため、刺しても痛点が感知しないんですね。そういう「痛点」を思い浮かべて頂けるといいんですけど、そんなイメージの「センサー」を自分の身体に高密度で張り巡らせている、という。針治療の針をも感知できる位のね。
TM: コンパルソリーはほんとに、「1mm単位」を競うフィギュアスケートの原点なので、そこに一度『原点回帰』出来たのは良いことかな、と思いました。

2013-14SP"East of Eden" @ 2013 Skate America
PP: そして、前回の取材では シーズン前ということで明かされませんでした、「(SP)エデンの東の読み解き方」、こちらも皆さん待望!なんですけれども、
TM: (笑) そうですねー、僕の"エデンの東"を見て頂いてスタインベックの「エデンの東」を手に取って下さる、そういう方も多くてですね、うれしい思いで一杯なんですけど⋯
やはり、芸術だったり文学もそうですけど、「三本柱」があるとされていて——「実証主義」「ニュークリティシズム」「受容美学」という、こういった三本の柱で僕達は物事を解釈してるんですけど⋯専門的に言えば。
PP: 専門的にお願いします!
TM: 実証主義やニュークリティシズムは、「一つの文学作品の解釈の仕方は一つしかない」という、「一つの答え」を導き出す考え方なんですね、そしてこれらの概念は客観科学(Objectivity in science)の領域にあります。それに対して、現代の解釈学や現象学の中では、受容美学という考え方があって。
受容美学というのは、「一つの文学作品を捉える個人個人によって捉え方が違う」「答えは一つじゃない」「一義的な解釈ではなく多様な解釈」「受容者の歴史性によって解釈される」等といった、そういう考え方なんですけど⋯簡単に言えばね。
 参考
参考
ニュークリティシズム: (New criticism) あらゆる視点や背景を排除して作品そのものに焦点を当てる
受容美学: (Reader-response criticism) 作品性は受け手に委ねられる
現象学: (Phenomenology - the philosophical study of the structures of subjective experience and consciousness) 経験則と意識下による、事象の哲学的な捉え方
解釈学: (Hermeneutics - the theory of text interpretation) 言語化された概念を理解するための解釈、その手法
TM: なので、「エデンの東の読み解き方」——もっと言えば、僕がコンセプトにしている(作中の) "timshel" という言葉の意味・解釈は、
PP: "timshel"、スタインベックは「(古語で)Thou mayest = You may」としていましたね。
TM: "timshel" 自体はヘブライ語で、日本語だと「汝、治むることを能う(あたう)」という難しい言葉になっていて、僕はその "timshel" という言葉に対していろいろ熟考してますけど、「僕の答えが絶対」とも「正解」とも言わないし、「"timshel" とは何ぞや?」と考えた時に 人それぞれ解釈の仕方があると思うので。
ただ、僕は、「自分の運命は自分で切り拓く」「人間には選択の権利がある」といったような、人間にとって無限の力を秘めており希望に満ちあふれている言葉 だと思います。
しかし "timshel" という言葉について僕が熟考したもの・僕の解釈を今ここで詳しく言葉で述べるのではなくて、僕の"エデンの東"、あのショートプログラムで体現することが僕の使命だと思っています。
ですから あえて、「僕は "timshel" をこのように解釈します」という詳しいことは、(にっこりと)ここでは述べません。
PP: (笑) 私達に "timshel" を委ねて頂いて。
TM: 「ショートプログラムを見て下さい」という。「そこで何かを感じて頂けたら、表現者として とてもうれしいです」ということしか今は言えないですね(笑)
PP: (笑) 各々、解釈します!
TM: それと、受容美学——つまり「作品を捉える人の主観的歴史性によって様々に解釈される」という視点で考えた時、僕は以前、「『エデンの東=ジェームズ・ディーン』というような、多くの方の中にある金科玉条(きんかぎょくじょう ☞ goo辞書)や色眼鏡を外して、僕の"エデンの東"として捉えて欲しい」とインタビューでお答えしたのですが、それは 自分のエゴであり間違った要求なのかもしれない、と考えるようになったんです。
「あなたの中にあるエデンの東に関する歴史性を一切排除し、僕の"エデンの東"を見て下さい」というこの考え方は、その人の歩んできた掛け替えのない、そして聖域でもある「歴史」に、他人の僕が不躾(ぶしつけ)に立ち入り強引に捻じ曲げようとする、そんなような行為なのではないかと思うんです。ですから、この場でその発言を撤回させて下さい。
これからは、皆さんの中にある様々な歴史という大海原の中で、僕の"エデンの東"が少しでも光り輝く存在になれるように、全身全霊で演じていきたいです。
PP: ⋯いろんなことが出て来て、皆さん 町田樹選手の"エデンの東"を全身全霊で解釈されると思います!
PP: 自分の解釈、なのですが、スタインベックの「エデンの東」の、日本語ではどう訳されてるか分からないんですけれども、「大人になること」という quote(名言)があって、
TM: うん、
PP: そう、「⋯ちくしょう、大人って なんだい。」って思った時に、もう世界が以前の輝きではなくなってしまう。それが大人になるという痛み(It is an aching kind of growing)、っていう、
TM: うん、
PP: そういう、(世界に)愛を渇望する、みたいな場面が最初に、(スタインベック・町田樹選手の)両方のエデンの東にあると思うんですけど。
TM: そうですね。⋯スタインベックって、エデンの東を含めて、「人間とは」とか「人間たる所以(ゆえん)」、「人間の哲理」——そういうことを熟考していった作家さんなのかな、と作品を読んで感じていて、今「怒りの葡萄」も読んでるんですけど、
PP: うんッ!(自分も、いつか ちゃんと読みたいです)
TM: (笑) その中にもいろいろ、人間とは⋯「こうあるべきだ」と 一つの答えを提示するんじゃなくて、登場人物が様々な葛藤の中で、もがきながらも人間という存在について深く考えていて、
PP: 種々の人生を物語に表してる、というような、
TM: うん、そうですね、「人間であること とは」とか、そういうことを考えさせられる作品が多いかな、とは思いますね。
だから、僕の"エデンの東"は、エデンの東だけじゃなくて、「怒りの葡萄」とか、スタインベック先生の他の作品からも大いにインスパイアされていますし、これからどんどん もっと僕の読書が進んで行くうちに、また "timshel" の解釈も深まったり⋯要は「人生経験」だと思うんですね。今後、もっともっと自分なりに "timshel" という言葉を考えていって、その精神をショートプログラムに注ぎ込みたいですね。
これからまた"エデンの東"を演じる機会がありますけど、1回1回どんどん成長していくんではないかな、と。中に宿っている精神も深みを増していくので。一見 一緒のようで、中にいる町田樹は違うのかもしれないですね。
PP: ⋯dedicated to スタインベック先生 (スタインベック先生に捧ぐ)、な"エデンの東"だったんですね!
TM: そうですね(笑) 1年前から構想していて、ほんとに打ち込んでいた作品なので。スタインベックはアメリカ文学を代表する作家で、そういう意味で、スケートアメリカで高い評価を得られたというのは光栄ですし、うれしいですね。
多分、日本人が捉えるエデンの東と、アメリカ人が捉えるエデンの東、っていうのは多少違うと思うんですよ、
PP: 言われていたように、ジェームズ・ディーンの映画のイメージでしょうね、日本人は。
TM: (小説は)聖書がモチーフになってるし、アメリカ人にとっては より特別だと思うんですね、「エデンの東」や「スタインベック」というのは。そのアメリカの舞台に立てて、僕の"エデンの東"を演じられたというのは 幸せだったな、と思いますね。
PP: そして「91.18」という自己ベストを更新されて。
TM: 僕の"エデンの東"を、僕が納得できるクオリティーで演じ切ることが出来たら、90点は超えてくるだろうな、という確信があったので、91点という数字には特に驚かなかった というか、むしろ、「思いを実証できた」というそのよろこびのほうが大きかったですかね。
PP: ⋯その、スケートアメリカの"エデンの東"後のお辞儀が、これまた未曾有のbow(お辞儀)で!
TM: (笑)
PP: ユーロスポーツの解説の方も「ダンサーみたい☆ スケートもだけど!(taking a bow like a dancer, skated like one, too!)」って!
TM: (笑) もちろん、曲が始まって終わるまでが「演技」なんですけど、氷の上に一人で立っている以上 そこは僕の舞台なので、最後まで「一つの舞台芸術」であるかのように、空間をクリエイトしていくことが大事なのかな、と思っていて、「氷を去るその時まで」しっかりと演じ切れるように心がけています。それは、(SP/FS振付の)フィリップ・ミルズ先生の教えでもあります。(FS)"火の鳥"もそうですし、
PP: 入って来る時から、火の鳥が舞い降りてますね。
TM: そう、「キス&クライに座るまでが一つの舞台芸術」となるように、
PP: "エデンの東"のbowは、噛み締めるような delighted(嬉) で、
TM: うん、そうですね、
PP: アレ、毎回見られるんですね?
TM: (笑) 毎回 出来るようにがんばります。
PP: お願いします!
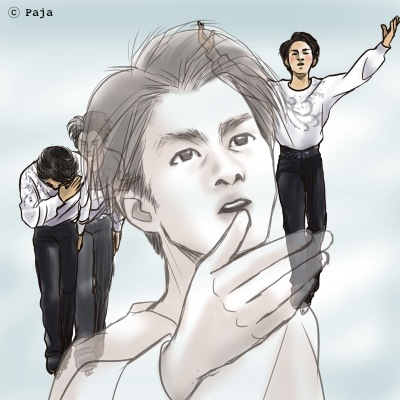
2013-14SP"East of Eden" @ 2013 Skate America