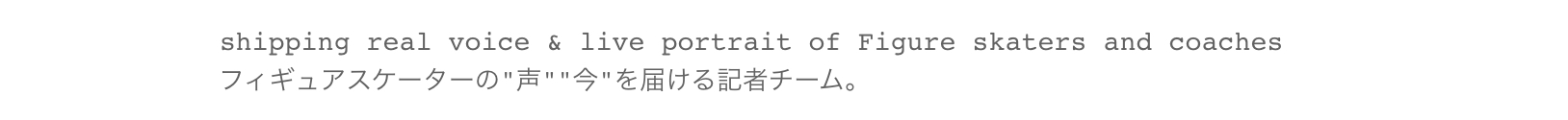Pigeon Post interviewed Tatsuki MACHIDA 町田樹選手 @ Kansai University in Senriyama 関西大学千里山キャンパス.
thanks to: JAPAN SPORTS for photos, PAJA for illustrations
by AIKO SHIMAZU 島津愛子
November 5, 2013 in Osaka

2013-14EX"白夜行" @ 2013 Skate America
PP: 構想1年の"エデンの東"ですが、振付師のミルズさんとのコラボレーションについてお聞かせ下さい。
TM: まずは、"エデンの東"の音源と、僕が考えた【timshel】や【サリナスの地に吹く風】というコンセプトをフィリップ・ミルズ先生に託しまして。「どうだろうか、制作できるだろうか」と。「僕が考えるに、この曲で・このコンセプトで 作品を制作できるのは、フィリップ・ミルズ、あなたしかいない。」というラブレターを送りまして、
PP: ♡ (笑)
TM: (笑) フィリップ・ミルズ先生も読書家なんですけど、スタインベックの作品を読まれたことがなかったみたいで、「早速読むよ!」と読まれまして、彼も「なんで僕は今まで、こんなに素晴らしい作家の作品を読まなかったんだろう」と、すごくハマっちゃってて。いろいろ話すうちに「樹、じゃあもう、実行しよう!」と。
だから、彼にも "timshel" という言葉の哲学があるし、僕と同じ思いを持って頂いて、コラボレーションが実現しましたね。
PP: 振付は共作、という感じですかね?
TM: 曲とコンセプトは僕が構築しましたけど、中の振りはフィリップ・ミルズ先生です。ただ、パフォーマーは僕なので、僕の意見も取り入れて下さって、話し合いながら より自分のフィーリングに合った振付にしていきました。
PP: 自分は、ミルズさんはフィギュアスケートの中では特異な振付師の方かな、と思っていて。コンテンポラリーのムーヴを、トランジションとしてではなく、演出的にフックとして効かせていて、
TM: うん、
PP: "火の鳥"だったら、こういうの(具象的な「首をかしげる鳥」の模倣ではなく その心象を刻むような振り)とか、アシュリー・ワグナー選手の"Black Swan(2011–12FS)"のスパイラルとか。なおかつそれを使い過ぎもせず、全体としては(コンテンポラリーの)決め決めな感じもなくて。
樹さんは、どういう振付師の方だと思われていますか?
TM: そうですね⋯彼が一つ決定的に違うのは、フィギュアスケート界出身ではない、ということですね。
PP: やはり。
TM: ABT(American Ballet Theatre・ニューヨーク 世界5大バレエカンパニーの一角)出身で、彼自身 火の鳥のプリンス役(Ivan Tsarevich)、魔王カスチェイ(Kostchei the Immortal プリンスの敵役)も演じたことがある、経験豊富なバレエダンサーで、フィギュアスケート以外のアートやダンス界に精通しているので、フィギュアスケート(競技)なんだけど「一つの舞台芸術を制作する」というポリシーをお持ちだと思いますね。
PP: 競技という枠の中でパフォーミングアートを追求する、という気概を感じますね!
TM: アシュリー(昨季まで)や僕とかの作品にはそれが如実に表れていて、「技のやり易さ、見せ方」は、どの振付師さんも気を配るところなんですけど、それもさることながら、氷・周りの環境⋯といった「会場全体を一つの舞台」として考えられていて。
大きな試合になると、テレビカメラの位置も自ずと決まってくるんですよ、そのテレビカメラの位置までをも計算して振り付けられるので。
「(競技だから)ジャッジが一番大切」と言ってしまえばそれまでなんですけど、(銀盤を360°取り囲む)会場のオーディエンスの視点、テレビに映されてそれが映像作品として残ること までをも考慮されています。
「このテレビカメラで この角度から抜かれた時に、このポーズが一番映えるよね」とか、「ここでこのポーズをしたら、こっちのオーディエンスやこのカメラにベストで映る」とか、そこまで細かく計画して作られているので。
TM: 「フィギュアスケートのプログラム」と言うよりかは「一つの舞台芸術の作品」としてクリエイトする、というのが、僕とフィリップ先生のコラボレーションの大きなテーマです。
そういう意味で、僕自身のプログラム制作だったり戦い方も 他の選手と異なると思います。

2012-14FS"The Firebird" @ 2013 Skate America
PP: "火の鳥"ですが、「『全然去年と違うわー』って思ってもらえるような感じに仕上げたい」と前回おっしゃっていた通りに、「全然違うわー」って思いました!
TM: (笑) "火の鳥"の一つの大きなコンセプトとして、「再生」というのがあって。
バレエ・リュス(セルゲイ・ディアギレフ主宰による20世紀前半のバレエカンパニー。火の鳥を初演。ストラヴィンスキー/ニジンスキー/ピカソ等を迎え、音楽/振付/美術の全ての面で新進的に、総合芸術としてのバレエを押し進める)やジョルジュ・ドン(モーリス・ベジャール主宰の「Ballet of the 20th Century」で活躍したダンサー)の火の鳥、手塚治虫先生の火の鳥等も、実は僕の"火の鳥"のモチーフになっています。
彼らの火の鳥に共通するのは「再生」「飛翔していく様」。その核となるものは 僕も引き継ぎ、継承させて頂いて、表現方法を「町田樹」らしくしよう、というのが僕の"火の鳥"の一つの大きなコンセプトなんです。
去年は 町田樹らしい"火の鳥"を公演できて評価も頂いて、とても光栄だったんですけど、それだけの作品をフィリップ先生と僕で創り上げたにもかかわらず、「僕がベストパフォーマンス出来なかった」っていうのが大きな反省点としてあって。
僕の表現だったりこの"火の鳥"が、まだまだ成長できる、伸びしろがたくさんある、ということを自分でも感じていたので、今シーズンもこのまま"火の鳥"を引き継ごうと思いました。そしてやはり「再生」という大事なテーマがある以上、ただ引き継ぐんではなくて。
去年 グランプリファイナル・全日本と大敗し、一度「死」を迎えたわけですね、僕の"火の鳥"は。で、そこからの「再生」ということだったので、より強く・より逞しく、神々しく、僕の"火の鳥"をもう一回飛翔させようと、オフシーズンを通してそのような作品となるように努力していて。
だからもう一度、バレエ・リュス、ジョルジュ・ドン×モーリス・ベジャール、手塚治虫、いろんな火の鳥を見直して⋯それこそ、また『原点回帰』。今シーズン、僕はなんでもかんでも『原点』に立ち返って、そこからもう一回 自分の歩むべき道を構築する、という作業があったんですよ。
そうやってもう一度、自分の中で"火の鳥"への想いを巡らせ、それをさらに強く演じようという覚悟を持って臨んでいました。
まだまだこの先 シーズンは続いていきますし、まだ僕の"火の鳥"も強く美しくすることが出来ますけど、スケートアメリカで ある程度のクオリティーのものが出来て結果も得られて(「174.20」で自己ベスト更新)、それもとてもうれしく思いますね。
PP: 振付は、ステップとコレオシークエンスとトランジションの一部が少し違うだけで、ほとんど変わってないですよね?
TM: ほとんど変わってないです。
PP: 同じムーヴでも、体の内側から外側に力が放たれているような、男性バレエダンサーな踊りで!
TM: (笑) やっぱり考え方が変わると⋯「作品に流れる精神」とかを見直すと、同じ動きですけど表現としてはまったく別物になってくる、というか。
PP: 身体が作品を「解釈」した、って感じですかね?
TM: そうですね、「脳も入れての身体」ですけど。
PP: 男性化、と言うより神格化で。
TM: そういう、僕の精神と⋯あとやはり、四回転が冒頭に2本入っているので。
四回転は確かに「高得点」ですよ、そういう「高得点を取ろう」とか、あるいは「勝ち負け」——「(フリーで)四回転を2本入れて勝とう」とか、そういう思惑は 僕の中ではあまりなくて。
PP: ⋯「あまりなくて」!?(ワクワク)
TM: (笑) なんで、四回転を2本入れてるかと言うと、それをハメることによって、「舞台」——会場を流れる、全ての気のストリームだったりエネルギーが「一段階 高次なものになる」というか。
やっぱり、四回転って「オォ!」って、惹き付けますよね。「四回転っていう技が持つ魅力・表現」がそこだと思うので。お客さんを釘付けにするというか、「一気に自分の世界に引き込む力」を四回転というあの技は持ってる、と僕は思うので。
そういう意味で、冒頭に2本『表現としての四回転』を入れることによって、さらに力強くそして神々しい"火の鳥"を創ることが出来るのかな、と。
PP: ⋯ソレを言う四回転ジャンパーは前代未聞ですね!(笑)
TM: (笑) ソレを言うためには、四回転の安定化はマストであって、それが実現したからこそ、
PP: 今 こうして言える、と!
TM: 四回転は僕の中で今、特別視していないし、他のジャンプと何ら変わらないし、「四回転は表現の一部である」と言えるところまで 四回転を引き上げることが出来つつあるので。それは自信に繋がってますね。
PP: 四回転を掌握している、という。
TM: 油断は禁物ですけどね。

2012-14FS"The Firebird" @ 2013 Skate America
PP: その四回転(トゥループ・4T)の反復練習で、回らずに軸を確かめる練習(T)に取り組まれていると思うんですけど、あれを羽生結弦選手も二回転(2T)でやられているんですよ、
☞ 羽生結弦選手 2012年11月のインタビュー (on Japan Skates)
TM: あ、彼 結構やってますね。
PP: そう、で、この前 織田信成選手に、「ルッツをエアで飛んでみよう」というコーナーをお願いして(笑)、
☞ 織田信成選手 2013年3月のインタビュー
TM: (笑)
PP: (笑) いつも教えて下さって。その時、「(飛ぶ前に)体を回して」のほうがジャンプは回るけど、良いジャンプにするには「(重心が流れないように)体を抑えて、しっかり上に上がろう」ということを言われていて、
TM: うん、
PP: テレビ朝日さんの Get Sports(10月14日放送) のインタビューを見ていて、「あ、樹さんも 同じことを言われている!」と。
TM: (軸を確かめる練習は)大西(勝敬)先生の指導なんですけど、四回転は特に「上に上がらないとはじまらない」というか。
TM: 昔の僕だったら、「四回転」は =「大技・難しいジャンプ」という固定概念が自分の中で存在して。なので、成功させるためには「いち早く回転に繋げなければいけない」という、余分な欲があったわけです。
それをなくすためには、まず ひたすら0回転(T)をやって。「高く上がる」ことをイメージしつつ、そこに「ベストの回転力を加える」ことを念頭に置いた練習なので、これらがマッチした時に うまく安定した四回転が出来るのかな、と。